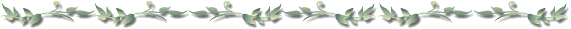
あれから一年が過ぎた
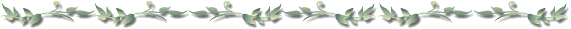
半袖のシャツ 黒のネクタイ
そして、礼服を衣装ケースから出す。
ズボンの折り目がいささかよれてしまっているが、男の一人暮らしだ。
そこは勘弁してもらおう。
きっと、こんなフォーマルな格好をしてくるだけで
彼女には、十分、僕の気持ちが伝わるはずだから。
通勤時間帯の混雑を避けるため、横浜へは出ず、大船から
横須賀線で鎌倉へ向かうことにした。
ふだん締めないネクタイと満員電車…
窮屈で仕方ない。でもそのことで気持ちがまぎれたのは事実だ。
大船駅で横須賀線に乗り換えると、うそのように人は減った。
電車の中はガラガラだ。誰もいないボックスシートに腰を下ろし、
車窓を流れる景色を眺める。
とたんに、故人に会いに行くのだという厳粛な気持ちになる。
あれからもう一年、いや一年以上になるのか。
同僚の女性ライターが亡くなった4月の夜のことを、
まだ昨日のように思い出せる。
HIVの感染が悪化による免疫低下…多臓器不全による衰弱死だった。
僕がかつて見たことのない孤独な死だった。
一人の人が亡くなろうとしているのに、誰一人として
彼女の元へ集おうとしなかったのだから。
彼女の恋人はおろか、血を分けた両親ですら…だ。
深夜に鳴った電話で、彼女が危篤状態に陥ったのを知った。
慌てて病院に駆けつけると、僕以外には誰もいない。
彼女の主治医がいうには、アドレス帳にある電話番号に
電話を全てかけたのだが、誰も病院に来ようとはしなかったそうだ。
中には、彼女が危篤状態に陥ったことを知らせると、電話を切った人もいたそうだ。
結局誰一人として病院に来ようとしないので、アドレス帳の最後のページにあった
僕の所に電話をかけてきたらしい。
「君のことは忘れないから、忘れないからね」
彼女の命の灯火が消えていく数時間の間
僕は彼女の手を握り、ずっとそう言い続けた。
熱に浮かされ、浅く速い息をくり返しながら、彼女は何度も力無くうなずいた。
やがて僕の手を強く握りしめると、ひとしきり切ない息を吐いて、
彼女は、朝焼けの中、天へ旅立っていった。
時の過ぎるのはあっというまだ。あれから一年が過ぎた。
「娘に会いに来ていただけないでしょうか」
そう連絡をくれたのは、彼女の父親だった。
電話を通じて聞こえてくるその声に、最初は怒りを覚えた。
「世間体だの何だの言って、自分の娘の臨終の場に足を向けようともしなかったのに、
今さら何を言ってるんだ」
ほんとにそう怒鳴ってやりたくなった。
そもそも彼女がHIVに感染したのは、彼女に何の非もない。
交通事故の手術の際に使われた血液製剤でHIVに感染したのだった。
その後、彼女は社会から想像を絶する差別を受けることになる。
彼女の両親は、社会の不当な圧力から彼女を守ろうとはしなかった。
「世間体」という言葉に逃げて、彼女を差別という猛威から救おうとはしなかったのだ。
「松沢さん。嬉しいですけど、私と一緒に仕事はしない方がいいですよ。
びっくりするくらいの圧力がいろんな所からかかってきますから。私……エイズなんです」
医学系雑誌の仕事のオファーをもらい、彼女にペア
(大きい仕事の場合、複数のライターが一緒に仕事をすることが多い)
として一緒に仕事をしてくれるように、頼むと、そんな返事が返ってきた。
正直驚いたが、HIVに感染していることと、仕事は何の関係もない。
それにHIV自体、非常に感染力の弱いウイルスで、一緒に仕事をすることはもちろん、
取材などで会う人たちに感染する恐れはない。
「そんな不当な圧力に屈するくらいなら、ライターなんてやってられないよ。
一緒に頑張ろう ね?」
泣き崩れた彼女を励まして、仕事を二人で進めた。
彼女の言うことは事実だった。
ありとあらゆる仕事の妨害や、あからさまな中傷を受けた。
僕が性行為で彼女にHIVを感染させただのといった、
目を覆いたくなるような怪文書は当たり前。
あまりに激しい妨害に、仕事の取引は数件停止に追い込まれた。
やがて妨害は、仕事を離れて日常生活の場にまで及ぶようになった。
最終的には、法的手段に訴えて解決をみたが、
世の中に、理不尽な差別があるということを僕は身をもって知った
あれから一年が過ぎた。少しだけ、僕の中にいる彼女の笑顔や仕草が遠のいた気がする。
僕はあれから、どんな一年を過ごしてきたんだろう。
なだらかな坂道を歩いて、彼女が眠る丘の上の墓地へ向かう。
ほどなくして、僕に頭をさげる二人が目に映る。
想い出の笑顔とよく似た二人。彼女の両親だった。
彼女の両親に再会したが、憤りは感じない。
礼儀正しく大人の挨拶を交わし、彼女が眠る墓地へ向かう。
花と線香をたむけ、祈りを捧げる。正直言って彼女の名前が刻まれた石碑に
何を祈ればいいのか分からない。
だって、彼女はまだ僕の中にいるんだから……
僕の中でまだ生きているんだから……
「今日は本当にありがとうございました。今さらこんな事を言っても
始まらないのですが、私どもが間違っておりました。
あの子があれだけ苦しんでいるのに、私たちはあの子を見捨ててしまった。
臨終の場に立ち会ってくださった松沢さんには何とお礼を申し上げたらよいか…」
「いえ…」
涙を流す彼女の両親に丁重な礼を述べ、彼女の墓前を去った。
誰が悪いわけでもないし、また彼女は誰も責めていないと思う。
そう思ったから、彼女の両親を責めなかった。
ひどい仕打ちをしたにしても、彼女にとっては両親である。
今また諍、いさかいを起こすことを彼女は望んでいないだろう。
それぞれの人の中にある、いろんな思いを洗い流す時間が
過ぎた気がした。
帰り道、一人で映画館に立ち寄った。
生前、彼女から映画に誘われたことを思い出したからだ。
「松沢さん、今度一緒に映画にでもいきません?」
「映画かあ…いいねえ。今の仕事が終わったら付き合うよ」
「じゃあ、約束ですよ」
「ああ、わかった」
その時の僕は、彼女にとって、明日という日が
やってくるかどうかもわからない、
あてにならない未来だということが分かっていなかった。
結局、彼女は、仕事が終わる前にこの世を去った。
あの時、なぜあんなことを言ったのだろう。
彼女の言葉の中に、仕事のパートナーとしての一線を越える
ニュアンスを感じたのは事実だ。
とはいえ、一緒に映画に行くくらいで、後込みする年でもなかろう。
あの時、僕は何をとまどったのだろう。
「彼女は病人なのだから」と、心のどこかで一線を引いて
彼女を真に友人として扱っていなかったのかもしれない。
もう二度とあの時に戻ることはできないが、あの時の約束を果たそう。
映画館の入口でチケットを二枚買う。
ソフトドリンクとポップコーンも
隣席に置いたソフトドリンクの水面が、映画の画面とともに揺れる。
彼女がそこにいて笑ってるようだった。
淡々と画面が流れた後、ラストシーン。そして明かりがつき
客が席を立ち始める。
「さよなら」
空席にぽつんと残ったソフトドリンクとポップコーンにそう言い残すと
僕も映画館を後にした
