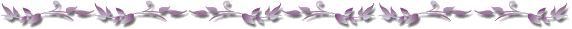
それぞれの想い
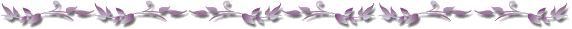
電話の向こうから聞こえてくる女性の声に、まったく心当たりはなかった。
それにもかかわらず、相手はあまりにも僕のことをよく知っているので、
妙な気分になった。
受話器から、どんどん不愉快な気分が流れ込んでくる。
正直言って、いたずら電話に付き合うほど僕はひまじゃない。
ただ、なんとなく電話を切るのが忍びなかったので
話を聞いていたのだが、そのうち
短気を起こさなかったことを感謝することになった。
もし、いたずら電話と勘違いして電話を切っていたら
永遠の別れになったかもしれない。
もっとも、そうしていれば、
こんなに切ない気持ちになることも、なかったのかもしれないが・・・・
電話の向こうの女性は、昔の恋人でもなく、女友達でもなく、古い友人の奥さんだった。
彼とはここ十年くらい会っていない。
(ちなみに最後に会ったのは、彼がまだ独身の時。
風の噂で、彼が結婚したことは聞いていたが、彼の奥さんと話すのは、
この電話が初めてだ)
「どうですか? 彼とはここ十年くらい会ってないんですけど 元気にしてますか?」
あからさまに不愉快な態度を見せた、そそうを取り繕うべく、
あいその良い声で尋ねてみると、意外な答えが返ってきた。
「主人は、亡くなりました・・・・・・・・・」
受話器を持ったまま、しばらく僕は言葉を失った。
ほんの一瞬の間に、彼の記憶が脳裏に浮かんで通り過ぎていく。
「うそでしょう・・・そんなばかな・・・」
しばらくの沈黙の後、やっとのことで、言葉を発することができた。
悪い夢を見ているのだ。そう思いたかった。
亡くなった?
あいつは俺と同い年で、まだ32だぞ。
必死に否定する言葉を探したが、次に出た彼女の言葉が、僕のその想いを叩きのめした。
「主人は、阪神大震災で亡くなったんです・・・・」
その言葉を聞いて、僕の気持ちは一気に萎えた。
彼が、過去の存在になってしまったのは、疑いのない事実だ。
だが、否定したい気持ちは完全には消えなかった。
なぜ今頃になって僕のところへ電話してきたのか
そのことがどうしても府に落ちなかったのだ。
しかし、そのかすかな望みも、次の彼女の言葉で無惨にうち砕かれた。
先日、奥さんが九州の彼の実家を訪ねられたとき、
彼の遺品の中に僕の名前の入った物を見つけ
あちこちで僕の住所を尋ねてまわって、今日やっと連絡をくれたのだそうだ。
がっくりと力が抜け落ちる。
「よろしかったら、お渡ししたいので一度お会いできませんでしょうか?
私、仕事で今日明日と横浜に泊まってますので・・・・」
都合のいい時間帯を聞き、その日の夕方
待ち合わせしたホテルのティーラウンジで奥さんと落ち合う。
時間より5分前に現れた女性は、彼の奥さんらしく
明るく聡明な感じの人だった。
とりとめのない話をしながら、お茶を飲み、彼の昔のことを話して聞かせた
もう、そのころには気持ちの整理ができていたのか、僕は冷静さを取り戻していた
「そうそう、松沢さんにお渡ししたい物というのは、これなんです」
「なんでしょう?」
そう言って、彼女が取り出した包みの中からは、1個の野球ボールが現れた。
手に取ってみると、僕の名前とプロ野球選手らしきサインが書いてある。
「あっ・・・」
とたんに記憶がよみがえってくる。
このボールは、昔小学生だったころ、ジャイアンツの王選手
(今のダイエーホークスの王監督)にサインしてもらった物だ。
それを、どうしても彼が欲しいとねだったので、仕方なくあげたのだった。
「私には分からへんのですけど、主人は、きっと大事にしてたんでしょうね」
男同士しか分からない、僕と彼しかしらない過去に、
奥さんは少しむくれながらそう話した。
「これは確かに私のものでしたが、今はご主人の大事な遺品でしょう?」
ボールを差し出されて、慌てて僕はそう尋ねた。
そうすると、奥さんは少しとまどった表情を見せながら、こう話した。
「私、春に再婚するんです・・・・」
「そうですか・・・・・」
きっと気持ちの整理をつけたかったのだろう。
察しは、当たっていたようで、彼女は
彼が亡くなってからのことをぽつりぽつりと話し始めた。
そのまま30分くらい彼女の話を聞いていただろうか?
最後に彼女は、彼が亡くなる忌の際の話をした。
「主人、なくなる間際にこう言ったんです・・・・
俺は、三途の川を渡るけど、お前はいい人をみつけて結婚せえよって
ほんま、ええかっこしいですよね ほんまに・・・・・」
「僕が彼だったら、やっぱりそう言うと思いますよ」
その言葉を聞いて、奥さんは泣き崩れた。
周囲の客の視線が一斉にこっちに向いたが、そんなことはどうでもいい。
「ただ、だまって彼女の話を聞くことが彼への供養になる」
そう自分に言い聞かせていた。
不思議と悲しいという気持ちは起きなかった。
それよりも、一本気な昔の気性を抱えて最後を遂げた
彼のことを誇りに思う気持ちでいっぱいになった。
本当は、悲しかったはずだ。
もっと、奥さんと一緒にいたかったはずだ。
理不尽な自分の死を毒づきたくなったはずだ。
そんな気持ちを押し殺して、その言葉を吐くのは
どんなに苦しかっただろう・・・・
こみあげてくる熱い物を何とか押さえると、
奥さんからボールを譲り受けて、僕はその場を去った。
帰りの電車の中で、そっとボールを手に取ってみた。
日はもう、かげりはじめていて、柔らかな日差しを窓ガラスに伝えていた。
その光を浴びて、ボールは赤銅色に輝いている。
その様をじっと眺めていると、初めて涙があふれてきた
「もう彼はこの世にいないのだ。二度と会えないのだ」
そんな言葉が脳裏を何度も駆けめぐりはじめると、涙が止まらなくなった。
「なんね 直ちゃん。そげなことで九州の男が泣いたらいかんぜ!!」
幼い日の彼の優しい顔が浮かんでくる。
「ああ、泣くもんか これは汗だ 涙じゃないよ」
そっと、遠い日の記憶の彼に呼びかけてみる。
だが、彼は微笑むだけで、何も言ってはくれなかった。
彼の奥さん、九州の御家族、僕、そして彼が人生の中で触れあった人たち・・・
彼の想い出を抱いたまま、みんな
それぞれの人生を、どう生きていけばいいのだろう
そっとボールを鞄の中にしまって、自分の心と向かい合ってみたが、
当然のごとく、答えは見つからなかった。
